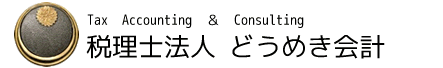日医年税(25)
平成18年8月2日
都道府県医師会
地域医療及び税制担当理事 殿
日本医師会 常任理事
内田 健夫
今村 聡
一、 先に国会で成立した改正医療法については、「医療法等の改正について」平成18年7月14日(地I60)にてお知らせしたところですが、医療法人の制度改革として主に次の2点が挙げられます。
(1) 特別医療法人にかわる社会医療法人が創設されたこと
(2) 医療法人の残余財産の帰属先が限定されたこと
この改正結果を受け、その後本会平成18年度医業税制検討委員会において検討が続けられましたが、この度一定の方向が出てまいりましたので、ご案内申し上げます。
二、 現在の医療法人では配当は禁止されていますが、出資者の退社や法人の解散に際しては、出資割合に応じて(残余)財産の分配ができるとされています。この点が、株式会社等の営利法人と変わらないとの批判を受け、厚生労働省「医業経営の非営利性等に関する検討会」において、持ち分のある医療法人を認めるか否か議論となりました。
本会の平成17年度医業税制検討委員会の検討では、従来通り持ち分のある医療法人を残して医療法人を以下の3つの類型として法制化し、これに応じた適切な税制上の措置を講じることを提言してきました。
(1) 公益性の高い医療法人 −特定・特別医療法人−
(2) 非営利性を徹底させた医療法人 −出資額限度法人−
(3) 持ち分のある社団医療法人
すなわち、持ち分のある社団医療法人の新設を認めないとする考えは、持ち分のある社団医療法人が地域医療において現実に果たしている役割、急速に増加している事実を無視したものであり、地域医療の現場に混乱をもたらしかねないこと。また、出資額限度法人への移行は法人の任意によるべきで、税制に十分配慮して促進することが必要であるとの考えであります。
三、 しかし、改正医療法では、以下の2類型の医療法人とし、持ち分のある社団医療法人の新設を認めず、既存のものについては経過措置として「当分の間」存続できることにされました。
(1) 社会医療法人
(2) 持ち分のない医療法人
この結果、同法が施行される平成19年4月1日以降においては、残余財産の分配ができる医療法人(持ち分のある医療法人)は設立できないこととなり、解散時の残余財産は「国または地方公共団体、医療法人、厚生労働省令で定めるもの」のうちから選定しなければならない、ことになりました。
改正医療法の具体的内容については、今後政省令で明らかにされ、また税制上の手当が予定されています。
本会といたしましては、今後、一人医師医療法人制度の健全な運営が図られるよう平成19年度の税制改正要望において要望し、政省令、税制等で対応してまいる所存であります。
四、 近年、診療所経営の近代化・合理化(家計と医業経営の分離)を目的とする一人医師医療法人制度については、設立の増加傾向は著しいものがあります。この度の医療法改正により、新たに医療法人化しようとする場合、改正医療法の施行日(平成19年4月1日)の前日までに設立するか否かにより、残余財産の分配が可能なものか否かが決まることになります。
つきましては、一人医師医療法人の設立に際しては、この度の改正を踏まえ十分に検討するとともに、各都道府県の医療法人設立認可スケジュールをご確認のうえ進められるよう、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。
なお、「個人開業医と医療法人の税制上の取扱いの差異」につきましては、平成17年12月医師福祉対策委員会答申「これからの医業経営の在り方について」(別添資料)において詳しい検討がなされております。参考としてご案内いたします。
添付ファイルがあります :announce-2130.pdf