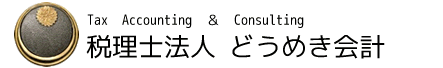法人税の世界では、同族株主の判断の基礎となります。
相続税の世界では、相続人の判断の基礎となります。
親族図とは、たとえば次のような図ですが、作成されたことはありますか?
┌────────────┐
│┌┴┐ ┌┴┐ │
││父┝┯┥母│ │
│└─┘│└─┘ ┌─ │
│ ┌─┴┐ ┌──┴┐ │
│ │本人┝┯┥配偶者│ │
│ └──┘│└───┘ │
│ ┌──┼──┐ │
│ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │
│ │子││子││子│ │
│ └─┘└─┘└─┘ │
└────────────┘
税法では、さまざまな場面で“親族”という表現が登場します。
ここでいう“親族”とは、民法上に規定されている親族の範囲をいいます
(民法725条)。
--------------------------------
民法第725条 (親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
--------------------------------
ところで、自分を中心とした親族図を描いたときに、上記のような親族の範囲となる人はどれくらいいますか?そして、自分が経営者であれば、経営している会社と取引のある会社を経営している親族はどれくらいいるか、把握していますか?
平成22年度税制改正で創設されている、100%グループ法人税制の各種制度ですが、個人を100%グループ会社の頂点である「一の者」とした場合には、100%グループ会社の判定要素に、個人の所有分はもとより個人の親族の所有分も取り込まれるため、注意が必要です。
たとえば、個人と複数の親族とが「一の者」となる100%グループ会社間で一定の譲渡取引を行い、損益を繰り延べた後に、100%グループ会社でなくなれば(たとえば“親族”から外れるような相続等が起きた場合)、繰り延べた損益を実現しなければなりません。
このように100%グループ法人税制は、自らの意図はなくとも調整を行わなければならない場合も起こりうるため、取引する会社は、どういう会社なのか、その会社は100%グループ会社に該当するのかどうかを把握し、取引をした時点のみならず、その後においても把握しつづける必要も場合によっては生じます。
まずは、100%グループ会社となるべき会社が存在するかどうかを知ることが先決です。親族図を作成し、どこまでが自分にとっての“親族”なのかを把握することからはじめましょう。
ご興味があるかたは、税理士で行政書士の資格のある当事務所にお問い合わせください。