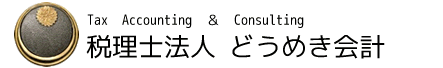被災された自治体へ直接義援金や寄附金を寄附することで、税の優遇措置を受けることができます。
この場合には、法人であれば、全額が損金となり、個人であれば所得税、住民税ともに税の優遇措置を受けることができます。(法法37③一、所法28②一、地税37の2①一、314の7①一)
また、個人が被災された自治体へ寄附する場合は、通常の住民税の寄附金税額控除の他、「特例控除額」が上乗せで受けることができます。
それでは総務省から公表されている、”計算方法”を参考に「特例控除額」を考えてみましょう。(平成23年度税制改正が成立した場合の、平成24年度分の住民税を計算してみます。)
参考:総務省HP「都道府県・都道府県・市区町村に対する寄附金税制の大幅な拡大」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/080430_2_kojin.html
「控除額の計算方法(PDF)」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/pdf/080430_2_kojin_bt3.pdf
例:給与収入700万円で夫婦子2人のケースの計算例
(4万円の寄附、所得税の限界税率10%、住民税所得割額293,500円)
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(※)から2,000円(平成23年度分までは5,000円)を引きます。
(※)総所得金額等(サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額)の30%が限度。今回の場合、限度額に満たない寄附額のため、寄附額全額。
40,000円-2,000円=38,000円
(2)(1)で求めた額に10%を乗じます。…[住民税の基本控除額]
38,000円×10%=3,800円
(3)所得税の税額軽減額(理論値)を求めます。
[夫婦子2人のサラリーマンの場合の所得税の控除率]
年収概ね600万円まで・・5%
概ね780万円まで・・・・10% ⇒例の場合は、こちらになります。
概ね1,200万円まで・・・20%
概ね1,430万円まで・・・23%
概ね2,380万円まで・・・33%
概ね2,380万円超・・・・40%
(4)90%から(3)の計算の際に用いた所得税の控除率を引きます。
90%-10%=80%
(5)(1)で求めた額に(4)で求めた率を乗じます。…[住民税の特例控除額]
住民税所得割の1割が限度です。
38,000円×80%=30,400円
住民税所得割の1割は29,350円であり、限度額を超えるため29,350円
(6)(2)+(5)=33,150円
なお、3月末の現段階において、寄附を受ける自治体が壊滅状態となっている場合や、あるいは受け入れ体制が整っていない自治体も考えられます。
受け入れ体制が整っているかどうかは、各自治体のホームページなどで確認していただくとよいでしょう。
ただし一部地域ではホームページのアクセスが集中して、なかなかつながらない場合があります。避難者名簿なども掲載されており、本当に必要な情報を得たい人が得られない場合も考えられます。また、寄附の手続きに受け入れる自治体の人員を要する場合もあり、各自治体への直接の寄附は、寄附する側の配慮が求められることは言うまでもないでしょう。