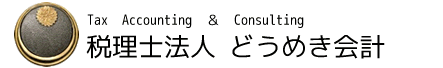8 判断能力が低下したときの「問題」とは?
・ 本人だけでなく周りも困る
・ お金の引き出しや財産管理ができない
・ 自分で医療・介護の手続ができず、健康状態が悪化する恐れがある
→ 第三者に法的に有効な権限を与えるための方法、それが「成年後見制度」。
9 判断能力の低下に備える「成年後見制度」
・ 法定後見制度;既に判断能力が低下している人が対象
・ 任意後見制度;まだ判断能力がある人が対象
10 「任意後見人」は何をするの?
判断能力の低下した本人に代わって、財産管理等の手続を行う人のことで、不動産 や動産など財産にまつわることはすべて代理でき、入院や手術のために必要な手続 や介護サービスの申し込みなど、本人の心身を守るために必要な手続ができます が、重大な手術を行うかどうかに対する同意権はありません。
11 「任意後見契約」が役立つ場面は?
① 財産を守れる
② 治療費や介護費用を調達しやすい
③ 現在の生活を維持できる
④ 親族の相続が発生したときに対処できる
⑤ 親族間のトラブルを防止できる
⑥ 家族の介護問題に対処できる
12 「任意後見人」は誰にする?
多くの場合は、子供や配偶者、兄弟姉妹、親、甥姪などの親族が引き受けることにな る。しかし、司法書士、税理士、行政書士、弁護士などの知識と経験のある専門家に 依頼ケースが増えている。
13 「任意後見人」の報酬は?
親族に依頼する場合は無報酬の場合が多いが、事務処理に多大な負担がかかるとき は、実情に見合う報酬を支払うのが望ましい。第三者に依頼する場合は、月額1~3 万円程度が相場。
14 「任意後見契約書」をつくる手順は?
① 受任者とよく話し合い、契約の内容を決める
② 公証役場に行ってその内容を公証人に伝え、書類の作成を依頼する
③ 必要な書類を預けて、作成日を予約する
④ 文案ができたら内容をチェックし、訂正があれば公証人に伝える
⑤ 予約当日、本人と受任者が公証役場へ行き、公正証書を作成する
15 2つの契約を同時に結ぶのが理想
「財産管理等の委任契約書」と「任意契約書」を同時に結んでおけば、本人の判断能 力が低下した場合でも、本人の保護を十分図ることができる。
16 将来、実際に判断能力が低下したら?
任意後見契約は、受任者や周りの人が家庭裁判所に「任意後見監督人を選任してもら うよう申し立て、その人が選任されたときに始めてスタートします。
17 「任意後見契約」がスタートしたら?
委任契約書の使用は中止し、任意後見人次のようなは誠実に職務を遂行します。
・ 財産管理や療養看護について、必要な措置を行う
・ 行った措置をすべて記録し、領収書などの資料を保管する
・ 3ヶ月に1度、任意後見監督人に事務処理の状況を報告する
・ 金融機関や不動産などの取引をする際は、法務局で「登記事項証明書」を発行して もらい、代理権の存在を証明する
・ わからないことがあれば、任意後見監督人に相談する