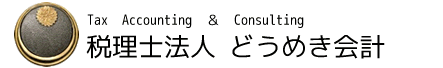1 「尊厳死宣言書」とは何か?
病気や事故などで回復の見込みのない末期状態になった患者に対して、生命維持治 療を差し控える、又は中止して、人間としての尊厳を保たせつつ、自然に死を迎え るための文書
2 「尊厳死宣言書」の具体的内容
① 尊厳死の希望の意思表明
② 尊厳死を望む理由
③ 家族の同意について
④ 医療関係者に対する免責
⑤ 宣言の効力について
3 「尊厳死宣言書」の作成方法は2通り
① 私署証書の認証;自分で宣言書を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける
② 通常の認証;公証人が作成する。証人は不要ですが、家族の同意を得ている場合 は同席してもらうのが望ましい。費用は、用紙代を含めて1万3000円程度。
4 「尊厳死宣言書」はどうやって使うの?
入院時に渡すか、事前に家族などに預けておく。宣言を撤回することもできる。
5 死後の気がかりをなくす「死後事務委任契約」
人が亡くなると、様々な事務処理が必要になります。何の用意もせずに亡くなると、 役所や近所の人などたくさんの人の手を煩わせることになります。死後の気がかりを 残さないために、生前のうちに死後の処理を第三者に依頼するのが「死後事務委任契 約」です。
6 自分の葬儀を生前に決めておく「生前契約」
「生前契約」とは、予め自分の葬儀の内容や予算を決めて、業者と契約を結び、将来 そのときが来た ら実行してもらう契約。
7 お墓は要らない、散骨を希望する場合は?
日本では、墓地以外に遺骨を埋葬することは法律で禁じられていますが、個人で節度 を持って行う限りでは、「散骨」は特に問題にはなりません。「散骨」とは、遺骨の 全部又は一部を細かく砕いてパウダー状にし、海中や空中、地中などにまいて個人を 弔うことです。最近では、「手元供養」といって、遺骨をパウダー状にして置物の中 に入れてリビングなどに安置したり、ペンダントや指輪に加工して身に着けて故人を 偲ぶという方法もあります。
8 献体や臓器提供をしたい場合は?
献体は生前に関係機関に登録し、臓器提供は「ドナーカード」に記入します。どちら も家族の同意が 必要で、献体と臓器提供は同時にはできません。
9 「エンディングノート」をつくろう!
「エンディングノート」とは、事故や病気、認知症など自分に万一のことが起きたと きに、介護や葬儀の希望など、家族や周りの人に伝えたいことを書いておくノートの ことです。これがあれば、自分が意識不明になったり、口頭で意思表示ができなく なった場合でも、家族に自分の考え方を伝えられます。
一般的に、ノートの前半は自分史(プロフィールや思い出など)で、後半は介護や葬 儀の希望、財産目録、遺族へのメッセージ、死亡通知の送付先などを記入できるよう になっています。
10 ひとりで死ぬことが予想される場合は?
① 日ごろから人の付き合いを大切にする
② 第三者が代わりに入院の手続や葬儀の手続ができるように契約しておく
③ 争議やお墓の用意をする
④ 家財道具や財産を整理・処分する